11/11/ 新潟市でNIC健康セミナー 救急医療の展望探る
- ke-yamamoto
- 2023年11月12日
- 読了時間: 2分

介護や医療の知識を専門家から学ぶ「みんなの医療・介護 NIC健康セミナー」(NIC新潟日報販売店グループ主催)が11月11日、新潟市中央区の日本赤十字社新潟県支部クロスホールで開かれました。新潟県医師会の堂前洋一郎会長、長岡赤十字病院の宮島衛・救命救急センター長、日本赤十字社組織振興課の玉木景子係長が講演。約50人の参加者を前に、救急医療の現状や今後の見通しを示しました。

堂前会長は「面積の広い本県では医師の確保が課題。地域医療は医師の犠牲の下に成り立っている」と説明。医師の時間外労働に上限を設ける2024年以降の「医師の働き方改革」に触れ、「特定の病院に医師を集約する必要がある」と訴えました。
その上で「新潟市は先進都市に比べ、救急医療機能が分散しており医師などの集約が不十分」とし、年間8千台以上の救急車を受け入れる新たな拠点として済生会新潟病院を選定したことを紹介しました。

宮島センター長は「救える命を全て救いたい ~災害医療とドクターヘリ」と題し、災害派遣医療チーム(DMAT)の役割などについて解説しました。
2007年7月の中越沖地震では新潟市民病院のDMATとして診療支援などに当たった宮島センター長。「発生当日は389人の患者が受診した。課題もあったが、DMATの初めての成功事案」と振り返りました。
また、本県のドクターヘリの出動件数(22年度)が2310件と全国2位であることを紹介。「新潟大学医歯学総合病院と長岡赤十字病院で県内の人口密集地域を重複してカバーしている」と語りました。

玉木係長は今後発生が予想される南海トラフ地震や近年増加している局地的大雨などの災害を挙げ、「自分自身で考え、行動することが重要」と強調。食品などの日常備品を減った分だけ買い足す「ローリングストック法」を提案しました。
また、今年5月に移転し県支部の新社屋について「通常の1.5倍の耐震性があり、災害時には対策本部が置かれる。倉庫には約8千人分の救援物資を保管している」と災害に備えた機能をアピールしました。
次回のNIC健康セミナーは12月2日、村上市の村上市民ふれあいセンターで開催します。

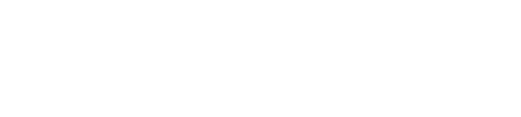
コメント