にいがた脳心センター開設記念市民公開講座「脳と心臓の声を聴く~いのちと生活を救う術(すべ)~」(9月28日)
- ke-yamamoto
- 10月31日
- 読了時間: 7分
(2025/10/31)
「にいがた脳心センター」開設を記念した市民公開講座が9月28日、新潟市中央区の新潟日報メディアシップ日報ホールで開かれました。脳や心臓など循環器病の専門家ら6人が登壇。抽選で選ばれた約200人の来場者が、疾病のメカニズムや治療、予防について学び、会場は熱気に包まれました。

にいがた脳心センター センター長(新潟大学循環器内科学教授)
猪又 孝元先生

県民の健康を守る大きな力に
脳卒中と心臓病を合わせた循環器病に対して、「この類いの病気になるのは仕方がない」という人ごと的な意識が、新潟県でとくに多く見受けられます。しかし、心臓病の終末期である心不全を考えても、実はいくつもの段階で対策が取れます。むしろ予防的な手立てが豊富な「やりようがある」病気なのです。
心臓はポンプの働きを担う筋肉を鍛えることができず、再生能力もないので、いったん傷むと元には戻りません。いかに心臓を傷めず、生まれ持った「貯金」で目減りを最小限にできるかが、心臓を長続きさせるこつです。
心臓が傷む代表である心筋梗塞は、心臓を養う冠動脈が詰まり心臓の筋肉が死ぬ病気です。動脈硬化によりプラークが壊れ、内皮が破けた箇所で血液が固まり血栓ができることが原因です。血管が詰まると6時間で心臓の筋肉は死に絶えるため、1分でも早くステント治療などで血管を開通させる必要があります。そのためには、患者さんご自身がいち早く的確に手を挙げることも重要です。救急車を呼ぶキーワードは、冷や汗を伴う胸痛です。ちなみに、プラーク破綻を予防するには生活習慣病管理と運動が有効で、なかでも最大の敵は高血圧です。
心臓病をいかに早く見つけるかも重要です。有用な血液検査が登場しました。BNPです。その数字で心臓のやりくり度が分かります。加えて、頸部(けいぶ)を見ることも重要です。起きたり座ったりしたときに、頸部の皮膚が揺れている人は高確率で心臓か血管の病気をお持ちです。心臓の専門医にぜひ診てもらってください。
「にいがた脳心センター」が、この7月に開設しました。患者や家族に寄り添う支援や相談、急性期から回復期・維持期、在宅へつなぐ医療ネットワーク構築など、行政、医師会と協働で進める組織です。電話や直接面談で県民の相談を受け付けていますので、気軽にご相談ください。循環器病を十分認識いただけるようスタッフ一同力を合わせ、新潟県民の健康を守るための力になることがわれわれの目標です。
にいがた脳心センター 副センター長(新潟大学脳研究所脳神経外科学教授)
大石 誠先生

新大病院核に多職種が連携
脳卒中は血管の障害によって起こる脳の病気です。血管が詰まる脳梗塞と血管が破れる脳出血、くも膜下出血の三つに分けられます。
中でも脳梗塞で最多の「ラクナ梗塞」や微細な動脈による脳出血が圧倒的に多いです。急に手足の動きが悪くなる麻痺(まひ)が起こりますが、基本的には点滴や内服により治療し、症状が改善することも多いです。
一方で心房細動と関連して血栓が血管に詰まる心原性脳塞栓ではtPA製剤で血栓を溶かしたり、カテーテル治療で血栓を抜き取ったりします。大きな脳出血やくも膜下出血では手術治療を行う必要があります。
時間の制約もありますので、治療するには早い方がよいです。いずれの場合も高度な麻痺や頭痛・嘔吐(おうと)、意識障害など含めた大きな症状が出ますので、様子を見ずに救急車を呼ぶべきです。
これら脳卒中の場合、急性期の治療と同様に大事なのが早期からのリハビリテーションです。治療後に症状が安定したら、早々にリハビリ専門施設に移り取り組んでください。家に戻る際は行政サービスなどを利用し楽しく生活する工夫をしましょう。
痛みや後遺症の治療も県内でできます。この一連の流れが脳卒中診療です。それぞれに専門家がいて多職種のネットワークで治療に当たります。
新潟県は面積が広く、人口もかなり多い。それをたった一つの国立大学医学部とその関連病院で全県の医療を担当しています。この特殊な医療事情を踏まえ、新潟大学病院を中心に中核病院、地方病院やリハビリ病院が連携、搬送・転送から情報交換までのネットワークがつながれば、県内どこでも同じ考え方の下、医療が運営できます。
「にいがた脳心センター」は、このような体制を多職種でつくり上げるための施設だと考えています。
土佐 一裕さん
(新潟県福祉保健部)

血圧測定の普及推進
新潟県、全国ともに、循環器病(心疾患、脳血管疾患)による死亡者数は、がんに次いで第2位。そこで2018年に循環器病に関する法律ができ、それに伴い本県も22年に「県循環器病対策推進計画」を策定しました。
健康寿命の延伸を大きな目的とし、循環器病の予防や正しい知識の普及啓発、循環器病を予防する健(検)診の普及や取り組みに重点を置いています。
循環器病は「やりようがある」病気なので、予防に関する取り組みに力を入れています。県民の健康寿命を延伸し、生き生きと暮らせる新潟県を実現するため、食生活、運動、デンタルケア、たばこ、早期発見・早期受診の5テーマで対策を立てています。
循環器病発症の危険因子の一つは高血圧です。本年度は5テーマに加え、にいがた脳心センターをはじめとする関係機関と「にいがたSTOP高血圧プロジェクト」を進めています。「まずは血圧を測る」ことを普及させ、測ることで各自が血圧を意識し、上がらないように取り組むことを目指します。
加藤 公則先生
(新潟大学生活習慣病予防・健診医学)

まずは、血圧を測定することが大切
人間ドックで尿の中の塩分量を調べ、その数値を伝えたところ、男女とも、みそ汁を1日2杯以上飲む人が減りました。測って数値を見せると人の行動が変わります。だから、自分の血圧を測ってその値を知ることが大切です。体重を測ると体重が減ると同じ理屈です。
この30年間で、47都道府県中、新潟県の健康寿命は第6位から34位に後退しました。それを改善するためには、血圧を下げて、脳卒中や心不全の発症を予防することが極めて重要です。そこで、脳心センターと新潟県では「にいがたSTOP高血圧プロジェクト」を始めました。目標は新潟県の血圧の平均を4mmHg下げることです。それによって、脳卒中や心臓病の発症が予防でき、必ず健康寿命が延びます。
まずは、血圧計があればどこでもいいので血圧を測りましょう。もし、上の血圧が130を超えていたら、家で血圧を測りましょう。朝は起床後1時間以内、薬を飲む前、朝食の前、トイレに行った後に測る「朝めし前の朝血圧」が大切です。血圧が130未満になるように運動して塩分を控えましょう。それでも、高ければきちんと治療を受けましょう
今井 遼太先生
(魚沼基幹病院)

体を動かし再発防ぐ
一般的にリハビリテーションといえば、機能回復の側面が強いですが、心臓リハビリテーション(心リハ)は、心臓病の再発や悪化を防ぎ安全に体を動かすことが目的なので、有酸素運動や生活指導などが中心の「病気を予防するリハビリ」といえます。
循環器病は正しい運動で予防できます。脳卒中と虚血性心疾患の危険因子である高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満は運動によって予防・改善が可能です。
「第二の心臓」であるふくらはぎにはポンプ機能があり、収縮時に静脈を圧迫し重力に逆らって血液を心臓へ押し上げます。ふくらはぎの筋力維持は、全身の血液循環の改善、動脈硬化や高血圧の予防にも寄与します。
心リハの一つ、かかとを上下に動かす「カーフレイズ」がお勧めです。立位でも座位でもOK。姿勢を正し1でかかとを限界まで上げ、2、3、4でゆっくり下ろす。分割でいいので1日100回ほどやり鍛えましょう。
自分で脈を測る検脈で体調の確認もしましょう。運動は1人では難しくても仲間と一緒なら続けられます。運動は循環器病を予防する「やりよう」の一つです。
布施 公一先生
(立川綜合病院)

セルフチェック有効
胃もたれや肩こり、あごの痛みが狭心症だったり、年のせいだと思っていた息切れが重症の心不全だったりすることがあります。見逃されやすい症状ですが、なかなか良くならなければ、心臓の病気を疑ってください。心臓病は早く気付けば予防・治療できます。
米国心臓協会発表のライフズ・エッセンシャル・エイトは、心血管の健康を守るため、食事や身体活動、血圧などの8要素を挙げ、各項目をスコア化しています。スコアが高い人は、心血管疾患や脳卒中などのリスクを40~60%ほど減らせました。
自分でできることとして、検脈で脈の乱れを感じるか、階段を上る時や前かがみになった時に息切れがないかなどを日々チェックしましょう。血圧も大事なので家でも測りましょう。
心臓病を予防する生活習慣は減塩、これが大事です。加えて、適度な運動、禁煙、節酒、睡眠です。
おかしいと思ったら、かかりつけ医を受診してください。胸痛や息切れなど、突然の強い症状が出たときは迷わず救急車を呼んでください。心臓病は早期発見が大切です。まずは気付くことから始めましょう。

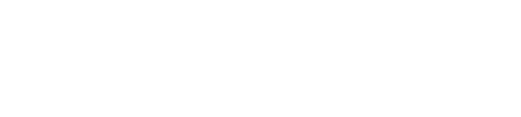
コメント