明日野家が聞く・健活インタビュー「子どもの『心』の悩み」
- ma-hara3
- 2025年8月20日
- 読了時間: 5分
(2025/8/21)
ちょっと気になるあんな病気、こんな症状ー。
明日野家の面々が県内の医師を訪ね、病気の特徴や治療、予防のポイントについてインタビューしてきました。明日からの健活にきっと役立つはずです。
病の手前 「個性」を尊重し 寄り添う

地域社会や学校、家庭で人間関係をめぐって、以前よりも「生きづらい」世の中になってきている。子どもたちが成長する過程で、「心の問題」をどう考えていけばいいのか。長岡市の県立精神医療センターで子どもたちを診察している吉永清宏精神科医長に聞きました。

よしなが・きよひろ 2011年、新潟大学医学部医学科卒、24年、同大大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻卒。新潟大学大学院医歯学総合研究科の地域精神医療学寄付講座特任助教や精神医学分野助教などを経て、25年、新潟県立精神医療センターに入職し現職。医学博士。日本精神神経学会専門医、子どものこころ専門医、日本児童青年精神医学会認定医。
―心の病気で学校を休む子が増えているって聞いたけど、「子ど もの心の病気」ってどんなものがあるの?
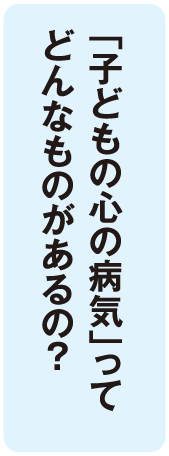
県立精神医療センターの児童精神科外来に来る15歳以下の患者さんの大半は、学校や家庭での暴言や暴力、自傷行為、不登校など、行動や心に関するさまざまな悩みの相談です。
その子たちには、コミュニケーション障害や自分の関心、やり方、ペースの維持を最優先したい「自閉スペクトラム症(ASD)」、集中できない、じっとしていられない、衝動的に行動する「注意欠陥多動性障害(ADHD)」、読む、書く、計算するなどが極端に苦手な「学習障害(LD/極限性学習症)などの特性を持つ「発達障害」があることが多いです。
発達障害は、生まれつきの脳の障害によるもので、本人の努力不足や親のしつけの問題ではありません。この障害の特性のため、いじめに遭ったり、居場所がないと感じたりして手を出すなどの逸脱行動をしてしまうことがあります。そこから不登校やうつ病、ゲーム依存などの2次障害を引き起こすこともあります。
―病院では、どんな検査や治療をするの?
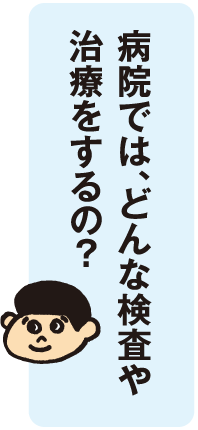
心理検査や知能検査などを行い、困りごとの原因を分かる範囲で数値化し可視化します。本人と親から話を聞き、どこでつまずいているのかを把握してから治療を始めます。軽いケースであれば、話を聞いて終わる場合もあります。
小さい頃に虐待やいじめなどのつらい体験(逆境体験)があると、考え方や行動にネガティブな影響が出る上、本当はそこで習うはずだった気持ちのコントロールや言語化を学ぶ機会を失います。まずはつらい心を癒やし、習わなかったことを教え、修正していく認知行動療法を行います。
症状が重い場合は、入院治療が必要です。当センターは県内で唯一の児童精神科病棟がある施設です。入院中は集団生活なので、ルールを守って生活をする練習から始め、できるようになったら、併設する県立柏崎特別支援学校のぎく分校小学部・中学部に通う練習をします。通えるようになったら地元の学校関係者や児童相談所などの支援者と元の学校に戻るのか、適応指導教室など別の居場所や対応が必要かということを相談し、外泊と試験通学を経て良ければ退院となります。
服薬によってADHDなどの症状や2次障害が緩和する場合、薬物療法を取り入れることもありますが、全員ではありません。認知行動療法が主流です。
―どこに相談すればいいの?

不登校や忘れ物が多いなど、ちょっと対応に困っていることがあれば、児童精神科を受診してください。ハードルが高ければ、かかりつけの小児科でもOKです。限界まで待ってからの受診だと症状が重くなり、回復までに時間がかかることもあるので、早めの相談をお勧めします。
「親子の心の診療マップ」には、問題に応じた相談場所などが載っているので見てみるのもいいです。
近年では、子どもがゲーム依存ではないかと相談に来る親が増えています。
WHO(世界保健機関)は、生活の中でゲームが最優先で、学業や生活などで支障が出ているなどの4項目に当てはまり、その状態が1年以上続くことをゲーム依存と定義しています。
この場合、ゲームを無理やり取り上げてはいけません。学校に行けず、家で叱られ、ゲームの中にしか居場所がないのに、それを取り上げられるとつらい。まずは取り上げず、関係をつくるように伝えています。最初に親が変わること。否定しない。そうすると家が居場所になり、家族が認めてくれることで、本人も変わろうとします。ゲーム依存は予後が悪い病気ではなく、回復できることが多いと言われています。
また、発達障害は環境次第やサポートの仕方でうまく過ごせるようになることがよくあります。忘れっぽいのであれば、約束を忘れないようにアラームを設定するなど、対策を講じれば「障害」は「個性」になります。周りが障害の特性を理解することも重要です。診断がついたから何が変わるわけではないですが、気を付けるべきことはあると思います。そして、不登校になったから人生終わりではありません。その後、多くの人が自立していることも分かっています。
病気は早期介入で良くなる率が高まります。精神疾患も同じ。特性と上手な付き合い方を見つけることで、精神科への通院が不要になる人はたくさんいます。3歳児検診や学校で指摘されたり、気になる特性があったりしたら、気軽に相談してみてください。
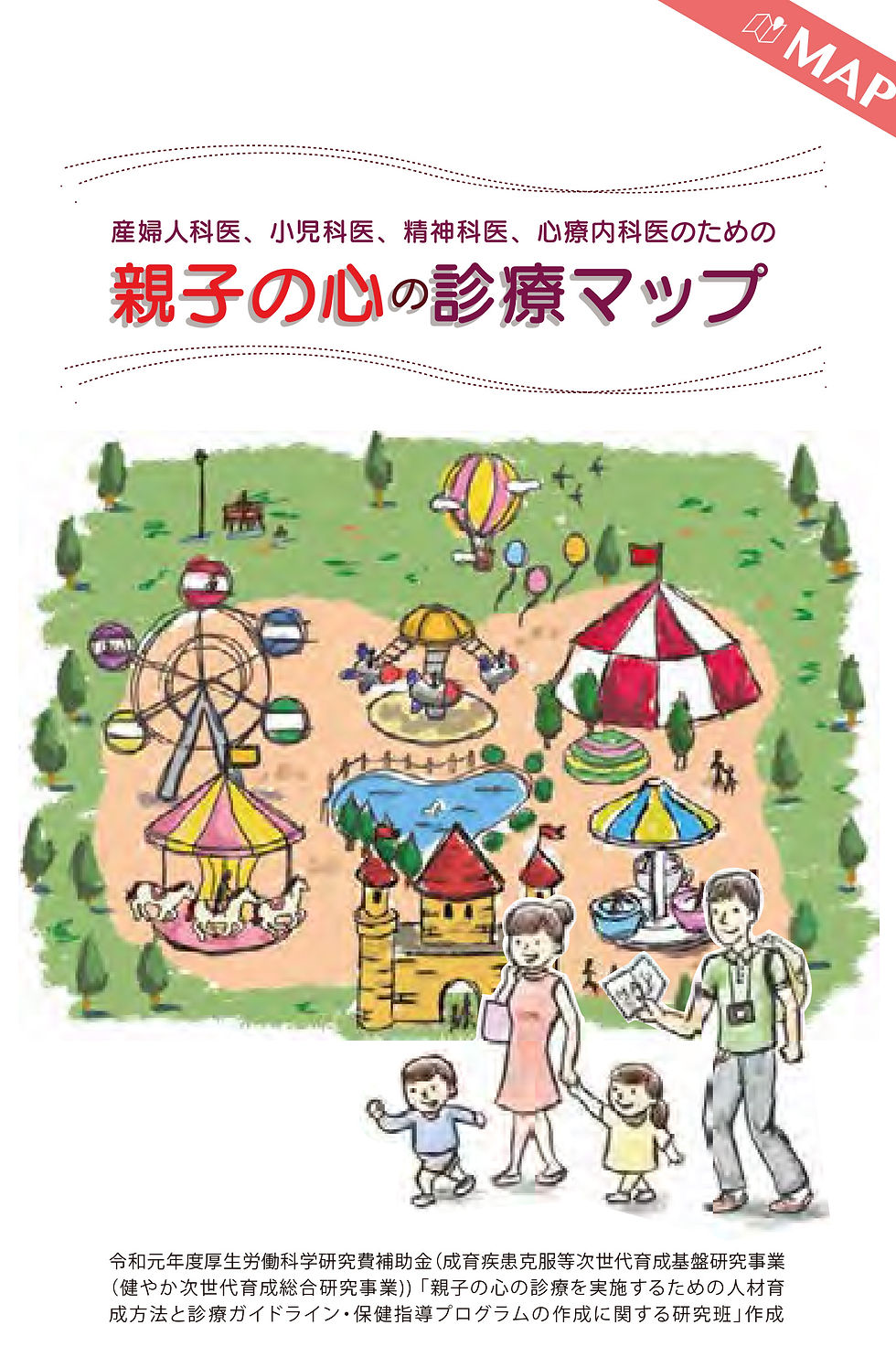



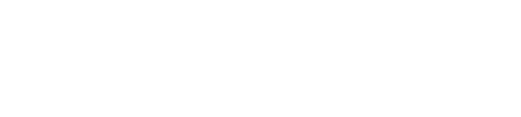
コメント