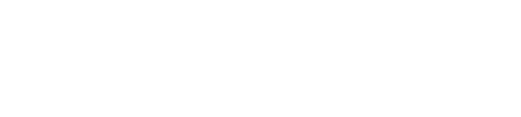患者さんの情報共有と警察医
- ma-hara3
- 2025年4月4日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年7月24日

(2025/4/4)
2007年から、新発田市の海岸に近い旧紫雲寺町で、夫婦で開業しています。当クリニックでは、プライマリ・ケア(病気やケガをした際に最初に相談する初期診療)を中心に、在宅医療、禁煙外来、発熱外来、予防接種などを行っています。今回は、普段患者さんの目に触れることの少ない「地域連携ネットワーク」と「警察医」についてご紹介します。
平塚ファミリークリニック 院長
平塚 雅英
地域連携ネットワーク「ときネット」
超高齢や寝たきり、認知症、身体の不自由など、さまざまな理由で通院が難しい方に向けて、当クリニックでは訪問診療を提供しています。2018年からは、在宅患者さんからの連絡を24時間受け付け、臨時の往診や看取りも行う「在宅療養支援診療所」としての役割も担っています。
在宅医療においては、ケアマネジャーをはじめとする介護サービス提供者や、多職種との連携が欠かせません。特に、24時間対応可能な訪問看護ステーションには、大いに助けられています。多職種の連携には情報共有が不可欠ですが、患者さんの情報はプライバシー保護の観点から、一般的なSNSや電子メールを使用することはできません。
新発田広域および村上地域では、「ときネット」という地域連携ネットワークが整備されており、同意を得た患者さんの医療・介護情報を高いセキュリティーのもと、多職種で常時共有することが可能です。訪問診療の際には、ケアマネジャー、ヘルパー、デイサービス、訪問看護師からの状態報告や、皮膚病変の画像などを活用し、診療の質を向上させています。
また、人生の最終段階に希望されるケアについて話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP、人生会議)」の情報を、担当者とリアルタイムで共有することで、日々変化する容体にも迅速に対応できるようになり、次の担当者が適切に配慮することができます。担当者チームが一体となることで、ご本人らしい生き方の選択を支援するとともに、ご家族の不安軽減にも役立てています。
警察医にご理解を

診療中の傷病に関連して亡くなられた場合、かかりつけ医や担当医が「死亡診断書」を作成します。当クリニックでも、ご自宅で最期を迎えられた方や、嘱託医を務める特別養護老人ホームで人生を全うされた方など、月に平均2名ほどの患者さんの看取りを行っています。
それ以外のさまざまな状況で亡くなられた場合は、「死亡診断書」と同じ書式の「死体検案書」が作成されます。亡くなられた状況や体表の状態から、死因や死亡時刻を推定し、記録します。特に医師が関与しない状況での死亡や、病気以外の原因が疑われる場合には、警察が事件性の有無を判断する必要があります。新発田警察署管内では年間約200件の警察取扱死が発生しており、そのうち事件性が否定できない場合は、新潟大学の法医学教室で死因究明が行われます。搬送先の病院で死亡が確認されたケースを除くと、年間約100件については、警察署の依頼を受けた開業医(警察医、警察協力医)が呼び出され、死体検案書を作成します。新発田市内では、私を含めた7名の開業医が365日間交代で待機し、私の担当した期間ではおよそ週に2件、年間にして30〜40件ほどの出動を行っています。
中には自死、孤立死、事故死などもありますが、最も多いのは、高齢の方が長期間の闘病を経ず、突然もしくは眠るように旅立たれるケースです。俗に「ピンピンコロリ」や「ポックリ」と言われるように、最期まで自分らしく自立した生活を続け、苦しまずに亡くなられる方々です。こうした方々は、もともとかかりつけ医がいなかったり、主治医が往診を行えない医療機関であったり、夜間や休診日に穏やかに亡くなられることが多く、その際に私たち警察医が最後にお身体を拝見し、お見送りする役目を担います。
ご家族にとっては突然の別れとなることがほとんどであり、戸惑いや悲しみの中にいらっしゃいます。書類作成の際にお会いできた場合は、少しでも心労を軽減できるよう、説明やお声がけをすることもあります。警察医は突発的な呼び出しが多く、診療との両立が難しいため、引き受ける医師が少ないのが現状です。そのため、警察医の後継者不足は県内各地で課題となっています。しかし、人生最期の診察を担う重要な役割として、私はこの仕事を続けています。
リコーダー演奏しています
高校時代は吹奏楽部に所属し、大学ではクラシック音楽同好会で管楽器の演奏をしていました。現在は、妻とともにリコーダーのデュエットでアマチュア演奏活動を不定期に行っています。これまでに、道の駅胎内、道の駅加治川、五十公野公園森林館、大天城公園、内の倉ダムなどで演奏を行ってきました。ひょっとすると、どこかでお会いする機会があるかもしれませんね。
平塚先生のリコーダー演奏の様子はこちら
(2025.4.4掲載)
略暦 ひらつか・まさひで
1965年、神奈川県生まれ。1991年、新潟大学医学部卒業。同大学医学部胸部外科学教室、県立新発田病院、新発田市国保紫雲寺診療所勤務を経て2007年、新発田市に「平塚ファミリークリニック」を開業。2015年から新発田警察署警察医、2020年から「しばた地域医療介護連携センター」センター長。趣味はリコーダーの演奏。
次回は平塚先生が親しくしている新潟大学医師学総合研究科・地域疾病制御医学専攻地域予防医学の高塚尚和先生です。平塚先生が警察医になりたての頃、日本医師会主催「死体検案研修会」で、新潟大学法医学教室で高塚先生の法医解剖の見学実習を受けました。新潟市医師会主催の死体検案の研修でも学ぶ機会があり、警察医の集まり・新潟県警察医会でも助言、指導をいただいたそうです。
協力:株式会社メディレボ