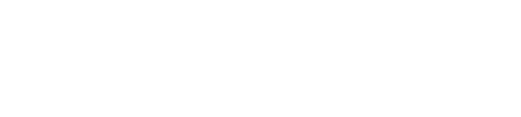放射線診断医の仕事と死後画像診断
- ma-hara3
- 2025年6月6日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年7月24日
(2025/6/6)

私は1988(昭和63)年に新潟大学医学部を卒業して、それからの40年弱、放射線科医として働いてきました。皆さんには放射線科の医師はあまりなじみがないかもしれません。「放射線技師とは違うのですか?」と言われることもしばしばです。ここでは、まず放射線診断医の仕事を、続いて私の専門分野の死後の画像診断を紹介します。
新潟大学大学院保健学研究科
死因究明教育センター副センター長
高橋 直也教授
ドクターズ・ドクター
放射線科医は、放射線を使ってがん治療を行う放射線治療医と、CTやMRIなどの医療画像を担当する放射線診断医に分かれています。放射線診断医は病院で行われる医療画像の管理と画像診断を担当しています。皆さんの中には、放射線科を舞台としたテレビドラマ「ラジエーションハウス」をご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。ドラマでは本田翼さんと浅野和之さんが放射線科医を演じていました。非現実的な部分もありましたが、放射線科の雰囲気や検査の場面は、わりあい実際に近いものでした。劇中で本田さんが「アメリカでは放射線科医はとても重要視されており人気も地位もある。彼らがいないと病院が成り立たないことから『ドクターズ・ドクター、医者をリードする医者』と呼ばれています」「放射線科医はすべての患者のCTやMRI画像を読影し、診断を下す重要な役割を担っています」と説明しています。
主治医の診断に影響

皆さんが病院を受診してCTやMRIの検査を受けるとき、どのような手順で行われるのでしょうか。まず、主治医は病気を診断するために必要な検査をオーダーします。オーダーの内容に応じて、放射線診断医が適切な検査方法を放射線技師に指示し、撮影のプロである診療放射線技師が検査を行います。撮影された画像は、放射線診断医が診断をして主治医に情報を伝えます。皆さんは診察を担当した主治医が、画像も診断していると思っているかもしれません。
もちろん主治医の先生方は、専門分野の画像所見には精通しています。しかし、症状とは関係ない部位に思いもよらない重大な所見が潜んでいる場合があります。さらに、日々進歩するCTやMRIなどの技術を、他科の医師がすべて把握することはできません。主治医の依頼から適切な検査方法を決定し、得られた画像から情報を最大限に読み取り、主治医に伝える。これが、放射線診断医がドクターズ・ドクターと呼ばれるゆえんです。
しかし、すべての病院で放射線診断医が画像を管理・診断しているわけではありません。実は、他国と比較して、日本には医療機器が群を抜いて多く存在します。世界中のCTの3分の1が日本にあると言われています。一方、放射線科医の数は世界の最低レベルです。新潟県内で放射線科医が常勤しているのは、新潟大学医歯学総合病院、がんセンター新潟病院、県立新発田病院、新潟市民病院、長岡赤十字病院、県立中央病院など、10余りの中核病院に限られます。現状では、検査に対して放射線科医は十分ではありません。
医療画像がデジタル化・配信されるようになり、画像は院内どこでもモニターで観察できるになりました。このため、放射線診断医は画像診断室のモニターの前で1日のほとんどを過ごし、患者さんと接する機会がなくなってしまいました。しかし、皆さんの目に触れないところで画像を通して患者さんの命と向きあう重要な役割を担っているのです。
解剖せず死因を究明
ここからは、バトンを渡してくれた高塚先生(新潟大学法医学教授)が書かれていた私の専門の死後の画像診断について紹介します。
日本は諸外国と比較して、解剖が行われる割合が非常に低いのです。高塚先生のような法医学の医師は200人ほどしかおらず、死因究明のために十分な法的整備が整えられていません。死因究明のための解剖は、何らかの事件に関わりがあるなどの事情がなければ行われません。どなたかが、突然倒れて救急車で病院へ運ばれ、残念ながら亡くなられたとします。こうした場合、診察では体内の様子はわからないことがほとんどです。日本には、前に書いた通り、非常にたくさんのCTがあります。そこで、死因を明らかにするために、亡くなられた方のCT検査が行われるようになりました。
私が、以前勤務していた新潟市民病院では、救命救急の先生方が中心となり2000年ごろから死後CTが行われてきました。これは、世界的に見ても先進的な試みでした。私は多数の死後CTを経験することができ、それを基に研究を行ってきました。新潟大学に異動した後は、法医学の先生方と一緒に死後のCTの検査と研究を進めています。
画像診断は、生きている方の病気を診断するだけでなく、亡くなられた方の死因を明らかにするためにも用いられているのです。

「放射線科医は画像を通して患者さんと向き合っています」=高橋教授画
(2025.6.6掲載)
【略暦】たかはし なおや 1963年、茨城県水戸市出身。1988年新潟大学医学部医学科卒業。放射線診断専門医。燕労災病院(現済生会県央基幹病院へ移行)、新潟市民病院などで放射線科医として勤務したのち、2013年より現職。死亡時画像診断を専門とし、医歯学総合研究科死因究明教育センター副センター長を兼任。
次回は 新潟大学医学部医学科臨床病理学教授 大橋瑠子先生です。病気の診断で最も重要な役割を果たす病理学が専門です。国内はもとより、ヨーロッパを中心として国際的に活躍されています。患者さんに直接接することの少ない病理医は、放射線科医と同様に「ドクターズ・ドクター」と呼ばれています。新潟大学医学部の臨床系ではただ一人の女性教授です。
協力:株式会社メディレボ